

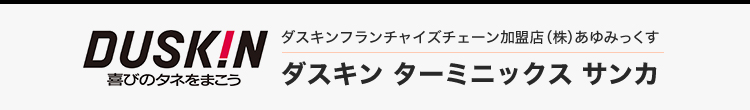

ダスキンフランチャイズチェーン加盟店(株)あゆみっくす
ダスキン ターミニックス サンカ
お久しぶりです、シロアリお役立ち情報担当の白石です。
年末に近付くにつれて、インフルエンザの流行が本格的になってきましたね。
私の家族は、妻と子供2人の4人家族なのですが、先週下の息子がB型インフルエンザにかかってしまい、翌々日には上の息子にもうつり、ついにその翌日には妻にもうつってしましました・・・。
そんな中自分は、予防接種を受けていた効果が絶大で、一人だけピンピンしております( `―´)ノ
皆さんも体調には十分お気を付け下さいね!

さて、今回の内容ですが、床下の構造について記事にします。
何でもそうですが、床下の構造も時代によって変化してきています。
今日は、昔ながらの日本家屋について、私なりにメリットとデメリットを解説していきます。
原始時代は竪穴住居や高床式住居などをはじめ、おウチの構造は変化を続け、現在ではコンクリートや鉄筋を使った構造まで進化を遂げています。
その中でも歴史の一番長い構造が木造ですよね。
皆さんの中でも一番馴染みのある構造かと思います。
一昔前では、和室が4間あり、親族が揃って集まったり、法事が行われたりと、いわゆる日本家屋と呼ばれる構造が主流でした。

全面木造で、日本特有の四季にも耐久性の高い、伝統的な構造です。
現在でもお寺や神社は、宮大工によって日本家屋の構造を取り入れています。
このブログをご覧になって下さっている方の中では、床下で遊ぶなんてことはしたことがないでしょうが、お寺や神社の床下は、非常に高く、昔の子供は鬼ごっこなどで遊んでいた時代もありました。
余談ですが、宮大工は年々減少しており今では全国で100人程度と言われております。
もちろん、一般家庭でも昔ながらの日本家屋の構造に、現在でもお住まいになられている方は大勢いらっしゃいます。
まずは、メリットからお伝えします。
一般家庭の日本家屋で作られている床下は、比較的高さが在ります。
これは、第一に風通しを考慮されているからです。
これまでも私のブログで、床下は風通しが重要とお伝えしてきましたよね。
昔の人は、第一におウチの寿命を考え、第二に耐震対策を考えられていたんですね。
そのことから、日本家屋は100年経ってもメンテナンスさえしていけば、問題なく住める素晴らしい構造なんです。
逆に今では洋風のおウチが目立ちますが、床下は全面コンクリートで覆い耐震が第一に考えられているため、気密度が高く、寿命も短いとされています。
次にデメリットです。
床下の下面が土のため、湿気がダイレクトに上がってきます。
風通しがしっかり行われていても、部分的に風通しが悪い箇所があったりすることで、カビが発生したりします。
その場合は、湿気を排出する対策が必要になります。
床下の湿気対策の記事はコチラ→https://www.ayumix.jp/sankablog/infomation/1428/
今回は、様々な床下の構造の種類の中から、昔ながらの日本家屋の類を解説させて頂きました。
“和風”が大好きな私には、日本家屋は憧れのおウチです(≧▽≦)
和室から中庭が見え、紅葉がヒラヒラと落ちている中で、そこ光景を見ながらお茶を飲む・・・
くぅ~最高っすね!!
あまりまとめれていませんが、次は現代の構造についてご紹介させて頂こうと思います!
